Wi-Fi6とは
インターネットの普及で欠かせなくなった無線LAN規格に「IEEE(アイ・トリプル・イー)802.11シリーズ」があります。それらに接続できる製品をWi-Fiとして認証しているだけで、無線規格の「IEEE 802.11 ○○」とWi-Fiはほぼ同じ意味となります。
これまで無線規格の「IEEE 802.11シリーズ」は通信速度を向上させ進化してきました。Wi-Fiと一言で言っても、それらの規格に対応した製品でなければ、通信速度が確保されません。その曖昧さを是正する意味でもWi-Fiの名称変更が行われたのです。具体的には
- 「IEEE 802.11 n」を「Wi-Fi 4」
- 「IEEE 802.11 ac」を「Wi-Fi 5」
- 「IEEE 802.11 ax」を「Wi-Fi 6」
と、バージョンアップする世代数ごとにWi-Fiを割り振られています。次世代移動通信「5G」は第5世代(Generation)という意味ですが、それと同じようにWi-Fiが名称変更された事は分かりやすくてありがたい事でもあります。
ところで、次世代の「IEEE 802.11 ax」の「Wi-Fi 6」ですが、10Gbpsの高速通信が可能になるとされています。「5G」も10Gbpsとなりますので、ちょうど次世代通信にあった規格ではあります。正確には「IEEE 802.11 ac」「Wi-Fi 5」の6.93Gbpsから「IEEE 802.11 ax」「Wi-Fi 6」の9.6Gbpsとなり、1.4倍の高速化できます。
しかし、これらは理論値にすぎず、干渉や遮へいなど、通信環境に左右されやすい無線通信では通信速度が思ったよりでない事が考えられます。好条件で限定的な環境であれば、そのメリットはあるでしょう。しかもスループット値はもっと低くなります。
スループットと実効スループット
「IEEE 802.11 ax」の「Wi-Fi 6」が10Gbps通信というのは多台数同時接続であるからです。実際1台に割り当てられる通信速度には限界があり、総合すると10Gbpsになるというだけのことなのです。
1台あたりの通信速度はスループットでわかりますが、それもまた理論値だと思った方が良いでしょう。
通信には様々な機器を介してデータを送受信されます。それらを考慮すると、通信速度は無線規格より遅くなるのです。その場合は実効スループットを参考にすべきです。ルーターやハブを介した場合の通信速度を表しているからです。
実際は昔の処理能力の低いルーターやパソコンを通してしまうとそれがボトルネックになり、さらに通信速度が下がってしまいます。
ただ、従来の1対1通信では待ち時間が発生してしまい遅延が生じてしまいますが、多台数同時接続のため、低遅延になる事は期待できるかもしれません。
Wi-Fi5もWi-Fi6もあまり変わらない!
Wi-Fi6が10Gbps通信を謳っていても、実効スループットが1Gbps程度なら、Wi-Fi5とほとんど変わりありません。
IoT時代になり、接続機器が増えて、多台数同時接続も意味があるようなものです。接続機器の少ない今の環境で、これ以上の低遅延もあり得ないところだと考えられます。公衆Wi-Fiのように多数の人が同時接続するような場合に限り意義のあるところでしょう。
Wi-Fi6の10Gbps通信だけに気を取られ、急いで対応しなければならないわけではないでのです。IoT時代が一気にやってくるならまだしも、まだまだ未来の規格であると考えても大丈夫でしょう。
お読みいただきありがとうございました。
引用


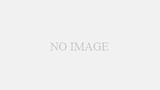
コメント