ムーアの法則が支えてきた経済パターン
ムーアの法則とは半導体の性能が集積度は18ヶ月ごとに倍になるというもので、この進化や恩恵を当たり前のようにまともの受けてきた世代でもある私にとって、ここのところのパソコンのCPUやメモリなど、電子機器類のスローペースとも思える、緩やかな進化に物足りなさを感じていました。基本的に半導体の性能はムーアの法則通り集積密度、プロセスを狭めることで、省電力化し、発熱を抑え、効率を上げていくことになります。よってこれまで通りに高密度化すれば良いのですが、それがここのところ止まっているのです。だいたいそのようになってきたのががスマートフォンが世に登場し始めた頃になると思います。逆に言えば、パソコンを進化、CPU、メモリの性能向上がうまく進まなくなったからスマートフォンやタブレットに生産をシフトさせっていったとも思えます。
ムーアの法則と言えどもいつかは限界が来る
日本もかつては、NEC、富士通と半導体メーカー、パソコンメーカーが全盛期がありました。確かにそのころはムーアの法則のように指数関数的に経済が発展しましたが、今は韓国や台湾など海外に生産がシフトし、依然としてアメリカのメーカーが主導していることには変わりはありませんが、東芝のメモリー事業が危うい中、日本だけが日の丸のように空洞化した産業になりつつあることは確かです。ただ、現在、半導体産業においてムーアの法則のように進化にかつての勢いはありません。そのように考えると日本メーカーがこれ以上、半導体産業に活を求めては、労力の無駄かもしれないのです。そういった意味では割り切り、切り替えていけることが幸運だと思いたいものです。
ムーアの法則が限界ではなく、オーバースペックと考えるべき!
確かにムーアの法則通りにこれからの進化を続けられたら、世の中は便利になっていくと思うでしょう。しかし、これ以上のスペックをどこに求めると考えた時、あまり見当たるところが正直ないと考えられないでしょうか。思い当たるところと言えば、日本が先行する4K8K規格ぐらいで、動画記録や画像処理にさらなる容量や効率化が必要なくらいで、普段使う仕事(ワードやエクセル)、作業や計算にこれ以上の求める意義はないように思えます。また、4K8K規格以上の高画質化は無意味だとすれば、CPUやメモリがそれを十分にこなせるほどのスペックがが満たせれば十分なわけです。現行ムーアの法則通りに次世代の7nmプロセスが確立されれば、それは可能になるでしょう。さらに半導体の高密度化を求めてもそれこそオーバースペックになりかねないわけです。
次元の違う技術革新へ
よって昭和後期からの半導体産業の進化と共に経済発展してきた理念やスタイルは終焉に向かっていると考えた方が良いかもしれません。しかし、それを残念に思うのは年老いた証拠です。なぜなら新しい形態は既に出始めているからです。それは人工知能や量子コンピュータです。量子コンピュータは現在の半導体で構成されるスーパーコンピューターをはるかにしのぐ高性能なコンピュータであり、個人所有できなくてもクラウドですべてが可能になる時代になるかもしれないのです。また人工知能によって今まで発想できなかったことすら可能になり、未知の領域にあります。そうであれば、いつかムーアの法則を懐かしく思える日も近いのかもしれません。

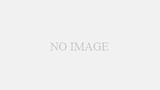
コメント