HDD(ハードディスクドライブ)はパソコンのOSやプログラムファイルなどを保存するCドライブとして定着してはいましたが、レコーダーに内蔵されたり、最近ではテレビ録画用外付けHDDとして、よく知られる存在になりました。しかし、その名は知られてきても、詳しくは知らないのではないでしょうか。そこで復習してみました。
一般的にパソコンに内蔵されるストレージとしてハードディスクは昔から使われていますが、パソコン関連ではフロッピーディスクやハードディスク、光磁気ディスク(MO)の磁気メディアを、音楽にはカセットテープや映像ではビデオテープといった磁気テープを記録デバイスとして使われてきました。昔はデータを保存しておくために磁気を媒体としたメディアが主流でした。言い換えれば、すべて「磁気で記録」という同様の技術でもあったわけです。MOもMDもCD、DVDの光ディスクのようなので、光磁気ディスクであったことに今さら気づきビックリです。
しかし、今ではDVDやBDなどの光学ディスクやSDカード、USBメモリ、SSDなどの半導体メモリが新たな記録メディアとして確立してきました。そのメリットは何なのか、ふと疑問に思うところです。
まず磁気メディアは名の通り磁気を利用したデータ記録であるため、磁気に弱い面があります。使用上、磁石など磁場を持つものは周りにあまりありませんが、電流の発生する電子機器には必ず磁場が発生しまうため、際どい所での使用を余儀なくされる技術的矛盾を抱えます。データを大容量化、細微化しなければならなくなるほど磁場の影響を受けやすいものです。
また知っている方も多いと思いますが、カセットテープなど磁気テープは外傷や熱に弱く、管理や保管にも配慮が必要となります。それらの面で磁気メディアには丈夫な金属やプラスチックなどで覆われていた構造になっていたわけです。そうなると、かさ張り、重く携帯性はなくなりますから、次第にUSBメモリやSDカードなどのリムーバブル(動かせる)メディアや外部の衝撃を受けにくい光学ディスクのCD、DVDに移行していったと考えられます。
それでも、今大容量データ保存にはハードディスクに敵うメディアはありません。やはり、サーバーにはHDDが最適です。
ハードディスクの構造上、少しの衝撃で故障の原因になったりしますので、あくまで据え置きとして考えた方が良いでしょう。また、USBメモリやSDカードはHDDより低電力です。また、HDDより多少容量が減りますが、光ディスクの方が故障時対応しやすく、データ破損もしにくく、劣化しにくいことで有利です。
それぞれ一長一短あるわけですが、技術的にも互いにしのぎを削ることで今後の技術発展に繋がれば良いと思っております。

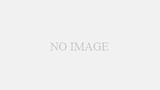
コメント