ようやく動いたIntel
Intelは7nmプロセスによる半導体の大量生産を予定していて、3~4年後の完成見込みなようです。
ムーアの法則の半導体の性能と集積度は18ヶ月ごとに倍になるというように今では集積回路チップ内に10億単位のトランジスタが搭載されるようになりました。
現在は14nmプロセッサー、その前は22nmプロセッサーを主体としてハイエンド機器などに搭載されています。
市場は14nmから次は10nmプロセスになる兆しがありますが、今回のIntelの発表はさらにその先の7nmプロセスということで、ずいぶん思い切った計画です。飛躍した技術革新となることに期待が持てます。
14nmから7nmプロセスは数字上2分の1ですので、単純に考えれば2倍の効率なのでしょうか。
コンピューターの要、CPU
コンピューターの進化はCPUの進化でもあります。いくらメモリ容量が上がってもCPUの役目でもある処理速度が上がらなければ意味がありません。
しかし、ここのところのそのプロセスルールは思うように進まず、コア数を増やしたり、消費電力を削減することによるCPUの性能を上げてきました。10nm、7nmプロセスと言った細微化はされず、根本的に変わらないところで効率化を図り、性能を強化してだけにすぎなかったわけです。
そこでふと疑問に思ったのです。スマホもタブレットもこれほどコンパクトになったのにもかかわらず、これ以上小さくする意味があるのかとか、扱えるビット数が64ビットとここ十数年変わっていないのに、単に小さくなるだけでは今までと性能としては同じなのではないかと思ったりするのです。
確かに集積するトランジスタの数が増えれば、より多くの計算や処理が可能になりますが、それはパソコンなど大きなハードであれば実現できるように思えるのです。例えば、スパコンがそうです。同じ集積回路であれば大小問わないのではないかと。
しかし、それには場所も電力も必要になります。それ以上にプロセス移行には意味があるはずです。
プロセスが何よりもスペックの違い
トランジスタは3つ接点により構成されていて、電気信号の有無で出力をデジタルの1,0の信号となるわけですが、まずその距離感がいくらナノメートル単位であろうが、それが数億個連なれば入力から出力までの相当な距離になり、処理時間も増します。
またトランジスタ内部のP、Nといったシリコンの面積、あるいは体積が大きくなればなるほど電気(電子)も必要になり、反応や機敏性が悪くもなります。
この14nmから7nmプロセスと1/2となることは、距離、面積、体積観点からから2倍、4倍、8倍と処理速度が向上するとまでにはいきませんが、そのようなことでもあります。
実際には使用電力の熱でもっと効率は悪くなるのですが、その消費電力すら減らせるのなら、やはり効率化が図れます。
14nmから7nmへのプロセスルールの移行は大きなスペックアップとなることでしょう。

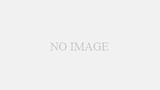
コメント