本ブログへの訪問、毎度ありがとうございます
お越しに頂き、ありがとうございます。ブログを書き続け、ようやく長文を書くことにも慣れてきました。皆様には読み苦しいところもあったかと思いますが、さらに、ためになる情報を発信できるよう精進しますので、今後ともよろしくお願いいたします。
文章を書くのが苦手
インターネット社会となりブログブームが訪れた時、自分には向いていないとか関係ない分野ものだと思っておりました。しかし、こうして思いもよらないブログを書いています。人生は思いもよらぬところで一人歩きするものらしいのですが、そんな具合でしょうか。とは言ってもそもそもブログに踏み切れない最大の理由は文章を書くことに苦手意識があったからです。
特に学生時代、理系であったため、文章を書くことに縁も少なく、文系のような文章力、国語力を身に付けてきたわけではありません。本を読むことすら専門性の高いものばかりで、一般的な文書を書くことへの経験値が絶対的に足りていないことや就職活動には小論文などあり、苦手意識がますます出来上がってしまいました。今でもありますが、ブログを書き続けて、文章にする少し要領を得たようにも思えます。まだまだ文章力は付いたとは言えませんが、それだけでもブログを書き続けてきた意義があったようにも思えます。
理屈っぽくなりますが、その要領や文章を書くためのコツを理系らしく分析してみました。
書くほどに文章力は身に付く
職人気質のあることは長所でもあり、最短の言葉で最大限伝えられることは理想です。しかし、以心伝心できるようにうまく行かないことが現実で、私のような学生時代、理系の方は特に片言の言葉で伝えようとしてしまいます。また、ひらめきや思いつきな言動も多いせいなのか、話がずい分飛ぶことがあります。それでブログで文章化すると、その時は自分で理解しているため伝えられていると思っていても、後々読み返し客観的になると、自分でも何を伝えたかったのか分からないくらいの文章になります。
それを解決するには、文章をかみ砕いて書いて伝えなければならない事が大事なことだとつくづく思い知らされました。分かりやすい文章にしていくと、自ずと長文になります。それが文章力というものかは分かりませんが、小論文などのように文字数ばかりを気にすることもなく、書くことがないと悩むことが少なくなりました。また書いている内に次に書くことが次から次へと思い浮かんできますので、逆に要約することを考えなければならないくらいです。量をこなすのから書けるようになることもありますが、それ以上に分かりやすい文章や説明があることが、結果として文章力となるように思えます。
時間をおいてから書く、話す
政治家は饒舌でスピーチがうまいため、即興で話しているようにも思えますが、実はそうではなく、普段から話す事をある程度、心の内(頭の中)に止めておくことができるからなんだと思います。大半は思いつきで会話もブログも書いているため、話がまとまらない時があります。ブログのテーマが決まってもすぐに書こうとするのではなく、そのテーマに合った話題をもっと引き出してから、あるいは、ねかせて、熟考させてから文章にすることで、うまい文章構成に仕上げられるように思えます。これを昔に気づいていたら、小論文などで思いつくまま書き出すのではなく、5分なり10分なり時間を取ってから書く手法になったかもしれないと、今さら言っても仕方のない後の祭りですが、今後に活かしたいです。
本を読むことは大事
いくらインターネット社会になろうが、知識を得るのに本ほど良いものはないように思えます。確かに情報はネットで探せますが、膨大な情報量から確かなものを検索するよりは、凝縮された本の方が時短でもあり、それ以上に知識として残ります。本を最近読むようになって、ブログを書ける自信にもなったようにも思えます。文章を書くのに手本となりますし、ボキャブラリーを増やせます。
自分の常識≠他人の常識
ブログを書いてきて、伝えること難しさを痛感したようにも思えます。自分の常識が他人の常識と同様なら言葉や文章は意味もなければ、文化にもなっていないでしょう。メディアも意図しない情報が世間を騒がせたり、報道にも規制が多くあるように、情報が世にもたらす影響力は大きいものです。だからこそ、学問にもなり得るものだと分かったのです。
今までは理系分野は技術や物として形になりますが、文系分野というと小説や文学のイメージばかりで、世の為になる意義を考えたこともないですし、懐疑的でもありました。しかし、伝えられなければ、後世に技術も伝承出来ませんし、文明は存続できません。歴史があるから、未来があるように文系分野の意義も少しわかったようにも思えます。

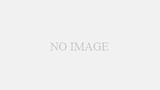
コメント