DRAMの大容量化
DRAM(dynamic random access memory)はパソコンのメインメモリーに使わる半導体メモリーで、コンデンサーに蓄えた電荷で一定時間データの保持できる構造です。随時、読み出し書き込みするコンピューターの主記憶装置として適しています。高画質化する動画再生や処理するデータ量が多い作業では、メインメモリーが大きいほど高速で大量のデータを扱えるため有利になります。まさに4K8Kと高画質になる今、映像再生やハイクオリティーのゲーム機、ゲーミングPCにはCPU処理能力も重要ですが、DRAMのメモリー容量もますます大容量化を求められることになるでしょう。
PCメインメモリーでは4GBでは少なく、8GBくらいないと快適ではなくなっていています。スマホのRAMですら3GBから4GBが定番です。HDやフルHDではそれくらいでなんとかなりましたが、単純にその4倍16倍の4K8K規格では、満足できるメモリー容量はいかほどになるかは察しがつくのではないでしょうか。
現在、DDRのデータレートはDDR3が800Mbps~2133Mbps、DDR4が1600Mbps~3200Mbps、チップ密度はDDR4がDDR3から2倍で40%の節電となりました。 そして、次世代メモリ規格「DDR5(Double Data Rate 5)」では、最高6.4Gbps、DDR4の2倍の帯域と密度を実現するようです。
「GDDR6」開発中!
GDDR(Graphics Double Data Rate)はパソコンのメインメモリDDRよりもグラフィックに特化したRAMのビデオカード専用DDRメモリー規格で 現在、最新がGDDR3とGDDR4の後継となるGDDR5で、PlayStation4になどのに8GB搭載されています。GDDR5ではDDR2の約9倍、GDDR3の約5倍、そしてGDDR4の約4倍のデータ転送に対応し、最大転送速度が理論値で28Gbpsに達します。
米MicronはDRAMの製造において、2017年末までに、現行の20nmから微細化を進めた1Xnm、1Ynmに製造段階へ移行し、年後半にも1Xnm製造のGDDR5を投入するとしています。また、GDDR5(8Gbps)の2倍の16Gbpsとなる「GDDR6」も開発中。
また、韓国SK Hynixは「GDDR6 (Graphics DDR6) DRAM」の2Znm 8Gbモジュールを発表しています。
かつてDRAM半導体メモリシェアトップの日本
半導体はCPUだけではありません。DRAMなどのメモリーも半導体の一つです。半導体メモリーDRAMがパソコンメインメモリの主役となり、市場を最初に制したのは米国でした。1970年代にはシェアが最大となり、1Kビット時代のIntel社、4Kビットでは米Texas Instruments社、16Kビットでは米Mostek社がトップとなりました。そのころから集積回路密度は18カ月ごとに2倍になるという「ムーアの法則」が30年以上続き、定説のようになったかと思います。
1980年代には日本がシャア首位となり、64Kビットでは日立製作所、256Kビットでは日本電気(NEC)、1Mビットでは東芝と日本メーカーが世界のトップとなりました。1986年には世界のDRAM市場の日本企業のシェアは80%にもなりました。バブル期もあり、活気に満ちた時代でもありました。日本半導体産業は活性化の正体はDRAMだったわけです。また、ファミコン、スーパーファミコンとゲームメーカーが急成長できたのも日本の半導体メーカーの躍進のおかげです。
しかし、1990年代の後半に韓国が日本を抜き、韓国のシェアは60%となりました。日本各社のDRAM事業は日立製作所とNECは統合しエルピーダメモリ設立させましたが、富士通は撤退し、東芝はMicron社に売却、三菱電機はエルピーダに吸収されました。日本のDRAMメーカーはエルピーダ1社となりましたが、結局はMicron社に買収されました。
いまや世界のDRAM市場を制しているのは韓国なのです。

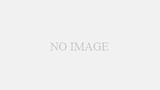
コメント